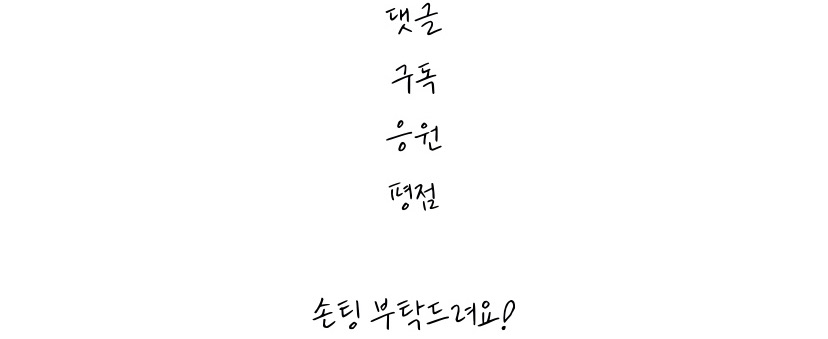記憶を歩く時間
やはり学校は悪いことがいっぱいの場所だ。開学して数日間私を大変にすることが少し多かった。特に開学初日から聞こえてくるイ・ジュンの名前と前政局の名前が最も大変だった。私もやはり前政局からイ・ジュンを見ているのが当たったが、他の人々はそうしなかったと言った。
内に南仏といってもいい。私が好きなものについては利己的な方だから。また、その人は私とは違う。他の人々は前政局を見てイ・ジュンではなくイ・ジュンの事件を思い出した。思い浮かべるだけで不足していたのか、今は膨らんで騒いで忙しかった。
「ミン・ユンギ、私は全政局にすみません。」
「もう来て?」
「…うん、そんな理由も知らず、人々の口に上がって下がっているじゃない。
開学序盤にはイ・ジュンの事件が私にとても痛くて私の考えだけだったようだ。ちょっと眠りに落ちた今からまわりを見回すと何も知らないまま、他人の口に上がり続ける前庭が見えた。他の子供たちもそうですが、前政局に私がとても利己的だった。チョンジョングクは私が泣いているたびに隣にいてくれたのに…
「ごめんなさい。」
「え?」
「まあ、あなたが直接理由を教えてもらえますか?」
言葉が詰まった。誰かが前政局に学校が恥ずかしい理由について教えてくれない限り、前政局は不快感を続けなければならない。それからまた口の軽い子供たちが言葉を移すこともしたら…。それも嫌だった。

「キム・ヨジュ、今のあなたは前政局に役立つことができない。むしろ負けになるだろう。ここであなたができることは理由に教えてくれたのか、まったく近づかないのか。二人のうちの一つだ」
また始まった。ミン・ユンギの率直で冷たい言葉。私を心配するのに冷たくなることを知って大きな打撃はなかった。ミン・ユンギの言葉を聞いてから悟った。前政局に申し訳ありませんし、他の子供たちの言葉が前政局の耳に入るのが嫌なら、私の選択肢は一つだということ。
私が直接前政局に打ち明けること。私はイ・ジュンの話を取り出すのが大変であっても前政局を守るためには必ずしなければならなかった。
「私は…前政局が大変なのは嫌だ」
半分に向かっていた足が止まった。その日から時間がかなり経った今、私は前政局とも交流ができた状況だった。だから現在の前政局と私は友人になってしまったし、私の醜い姿は前政局がみんな見て。もしも前政局がこの状況をしっかり立ち去ってしまったら今回は本当に耐えられないようだった。
「おい、お前は、」
「サムに話をちょっとよくしてくれ! 頼むよ!!」
私の唯一の選択肢に向かって行こうとします。私はそのまま振り返り始め、前庭を探し始めた。学校のあちこちを後ろに、前庭国見たという子どもの言葉の末に私が向かおうとするところは屋上だった。

廊下の一番下の階段を何度も登り、学校の建物で最も高い階に到着しました。私は息を数回大きく選び、大きくて硬い灰色の鉄の扉を開けた。
「剪定ㄱ、」
ドアを開けて前庭国の名前を歌おうとした瞬間、私の目の前に見えるのは屋上手すりにギリギリ立っている前政局だった。瞬間的にびっくりして声が出ないほどだった。少し震える体で一歩ずつ前政局に近づいた。
「お前、お前今そこで何してる、前政局…」
「え?ヨジュダ。」
前庭は私の声で手すりの上に立ってきれいに笑って、私はますます表情が固まった。思い出さないようにしても何度もその日が思い浮かんだ。屋上の手すりに立っているチョンジョングクと写真不良で薬筒を持って立っていたイ・ジュンが重なって見えた。
心臓がいっぱい詰まってくるように降りてきた。イ・ジュンではなく、もう一つの大切な人を失うのは本当にひどかった。またそんなことが起こるかと思い、不安になった私は刺身震えるように身を震わせた。
「お前まで負けたくないんだよ…」
私はそのまま首をすっかり下げてしまった。頭を下げるとすぐにそのままに落ちる涙だったし、屋上の床の上にはそのまま私の涙跡が残った。
涙が何滴くらい跡を残したのか、私の今後影が敷かれた。それは明らかに前庭の影であることを知る前に、私は前庭と目が合ってしまった。なぜか、両手で私の頬を包んでそのまま持ち上げた前政局のためだった。
涙をぶら下げて吊り下げてチョンジョングクと目が合うと、寂しい 心が泣き、泣き出てしまった私だった。前政局は慌てたのもしばらく、以内に被食一度笑ってはそのまま私を抱きしめた。

「毎回私はあなたが泣いているものだけを見るようです。」
前政局の懐に抱かれた私は、ほっぺたも知らず泣いた。奇妙に前政局の前では感情がぜひジェットコースターに乗る気分だ。気分が良かったとしても涙がジュルリュク流れ、最後に幼い子どもに泣き叫ぶ。
「泣かないで、ヨジュヤ。私たち今こんなに抱いているじゃないか」
かなり優しい声だった。いや、今は優しさを越えて甘くなるまで、ある前庭の声に私も知らずに彼の懐にもっと掘り下げた。私が本人の胸パックに顔を副秘的にし、両腕は腰を包んで安子私などを吐いた前庭の手が非常にしばらく止まった。
「…あまりにもタイトなのではないか」
「うん?今何と言った?」
「ああ、何もない」
私が頭を上げて前政局の顔をじっと見つめて尋ねると答えを避ける前政局だった。私は泣きが止まったにもかかわらず、前庭の懐が暖かく、しばらくを抱いていた。前政局もやはり私を切り離したりしたりしなかった。
しかし、私は見た。前政局の土徳であることが止まったとき、そっと見上げた前政局の耳が真っ赤に駆け上がっていたということ。