
09
「なんて女主は本当に来たの?
なぜこんなに久しぶりなの?」
「すみません、私も出たかったのですが。
最近とても忙しかった」
「いいね、もう見た。
何。早く座っています。」

「と、これがないこと。
話を連れてきた私は歓迎しないでください。」
こんにちはキム・ソクジンを捻れた。これまで仕事が忙しかったせいもあって、ユンギさんと時間を過ごして県生での道を切り開いたので、このような場所が少しぎこちなかった。
幸いなことに、私の喜びは友達の態度に心を置いた。それでも私には君もいてよかった。私の言葉で、ソクジンは私の顔をしばらく見ているよりも頭を回した。おそらく私がたくさん大変だということを知っている気づいた。
「しかし、ヨジュ。彼氏はいますか?
忙しくて会えないのか」
「え?」
「いいえ、なぜ、あなたは人気がありました。
今もこんなにきれいなのにいるかと思って」

「・・・エイヤ君は何をそんなこと聞いて
そうか。みんなモソルなのを知っているじゃないか」
私が驚いた目でソクジンを見つめると、ソクジンは友達に知らずにウィンクをした。なんだ君はどこまで知っているのに・・・。まさかジョングクさんが教えてくれたか。それではないようだった。そんなソクジンのために友人の関心は絞った。代わりに、なんだか分からない男の子の何人かが私のそばに近づいてきた。
「ここは空だから
座ってもいいですか?」
「え?うん」
「それではどんなスタイルが好きですか?」

「·····。」
「好きなスタイル・・・。
思ったことないけど」
前にユンギさんを見たソクジンは言葉なしで私を見つめて唾液を飲み込んだ。それでも悩みちょっとやってみると笑顔の男の子に考えに浸った。ソクジンが言葉のように、私はユンギ氏に会う前までのモソルではなかった。すぐ別れた彼氏がいるが、それほどお互いが好きではなかったし、本当の愛を始めたのはユンギさんだった。片思いをしてみた相手の共通点を探してみると・・・。
「・・・いったん目がそっと
破れたらいいな」
「え、私は猫像なのに」
「肌もやればいいなぁ・・・
性格は大丈夫ならいいです。」
「それはぴったりなんだ・・・。実はヨジュヤ
私はあなたの番号を受け取りたかった、」
「そして自分が好きな人
周りの人の神経がすごい
書いて欲しい。肌もただ
白ではなく青白くなるほど。
そこに立つけど食べて料理もよくしてまた、」
その時気付いた。私は今何をしているの?ただこれはユンギさん紹介しているじゃないか。頭が濃い。そんなことにあってもまだ忘れていないのを見ると、私も本当に狂ったようだった。
その男の子も友達もそしてソクジンも私を見て、不思議な表情をしていた。だから、それが・・・。頭の中がユンギさんでいっぱいで言葉をつなぐことができなかった。急いで席を迫って立ち上がり、突然体が良くなったと巡った後、酒場の外に逃げるように抜け出した。

「·····。」
そして、その状況を後ろからこっそり見守っていたジョングクは、状況が面白く帰るというように笑いを打った。なんだ、もうキム・ヨジュまでミン・ユンギと同じように流れていく。そのようにジョングクは帽子をすっかり押しつけて女主の後に従った。
キム・ヨジュは吸血鬼のような人が好きです。
そしてそれを代用できるのは、ツヤしかない。
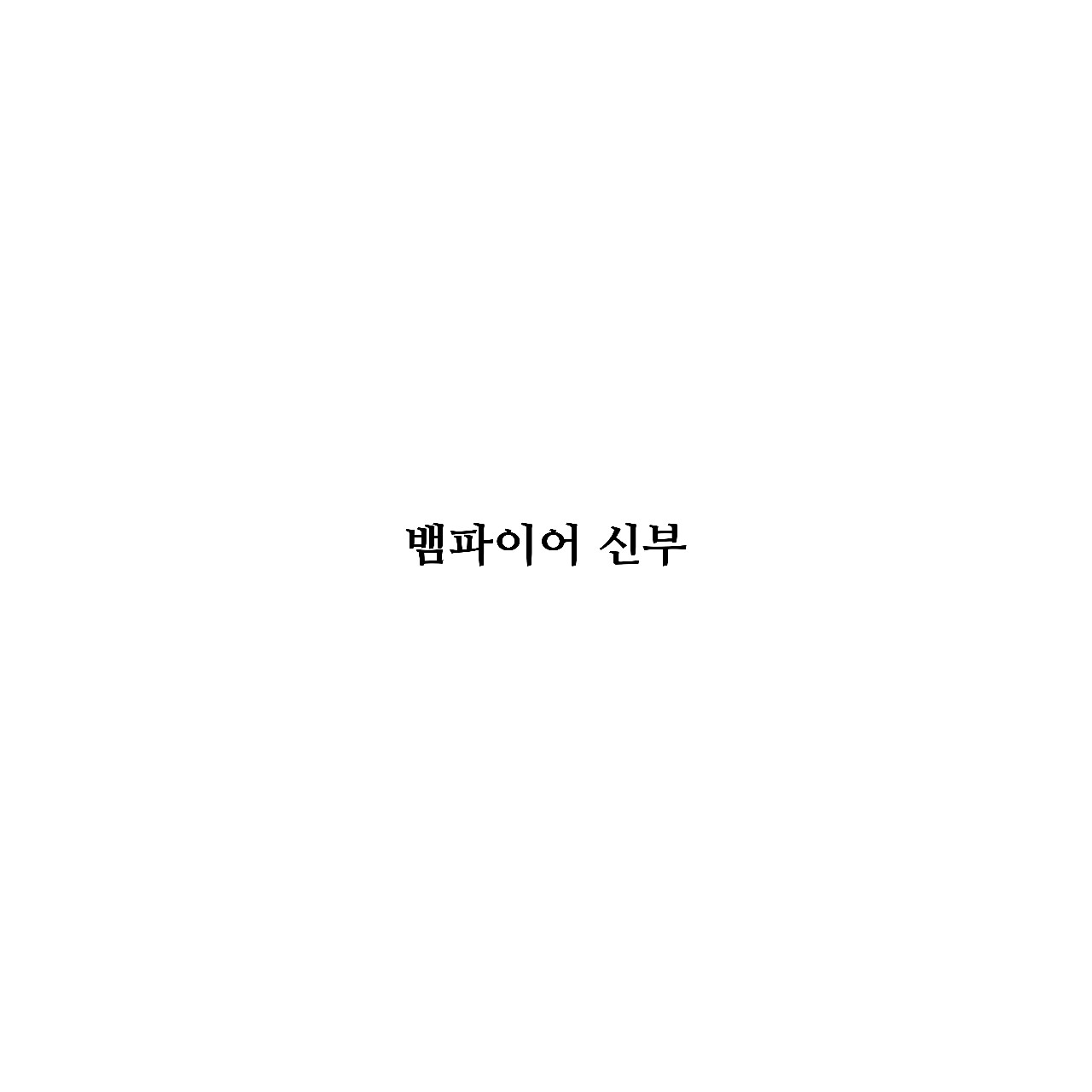
外に出ると冷たい空気が体に当たった。それでもまだ夕方にはちょっと肌寒いかより。考えに浸っていて上がらなかった酒気が心がちょっと平穏になると、それこそフック上がり始めた。すぐに首と顔が赤くなり、歩き方もねじれた。
タック。

「危険です」
その時ジョングクさんが現れて私の手首を握った。気をつけてみるとすぐ目の前に街灯があった。延伸ありがとうございました。
ここはどうやって来たのかという質問にジョングク氏は別言しなかった。ただ、どうしたらいいですか。それがすべてだった。私もあまりキャッチしたい気分ではなく、そうしてしまった。ジョングク氏は夜道が危険だから連れて行くと言った。
「大丈夫です。まだ8時しか
ダメなんですけど、何・・・。」

「だから連れて行くという
でしょう。 8時になったからです。」
「·····。」
「行きましょう」
もっと大丈夫だと言えば、悪口でも本当らしい表情に勝てないと分かると答えた。その後、ジョングク氏は何も言わなかった。私がねじるたびに腕をつかんでくれるのが全部だった。そんなジョングクさんと違って私は聞いてみたいことが多かった。例えば・・・ツヤさんとか。
恥ずかしさを和らげ、慎重にユンギさんはどのように過ごすか尋ねた。それも煩わしく答えないようにしたいとしなくてもいいと面倒だった。言葉を終えたら思ったよりもっと売れた。ああ・・・ただ口を閉じて行きます。静かに頭を下げた。

「お元気です」
「・・・・・・あ。」
「考えよりはね」
「はい?」
「お酒に突っ込んで、うるさいを少し
することを除いて大丈夫です。」
ユンギさんの状態があまり良くないようだった。心配になってもっと病気のデンがないか尋ねようとしたが、不思議に見てみようかと思った。実はそうだった。前に愛していた人を忘れずに私のナイフで切ろうとしたユンギさんを心配するというのは狂ったことも変わらなかった。
そして、しばらく経って靴のためにかかとのかかとが苦しかった。そうではありませんが、ねじれたのですが、今は絶えず、ジョングク氏は私が病気であることに気づきました。

「ここで少し待ってください」
「はい?」
そのようにジョングク氏は私の通りのベンチに座って置いてどこかに飛び込んだ。数分ほどジョングクさんを寝て待つと何かが詰まったショッピングバッグを持ってきた。走ってきたのか息がガパ見えた。
「申します。」
「これを買おうと・・・、そう
ジャンプしたの?」

「ただマートが少し遠かったのです。」
ショッピングバッグの中に入ったのは三線スリッパだった。しっかりした顔でじっとしているとジョングクさんがしゃがんで座って身近に靴をはがしてスリッパを履いてくれた。スリッパを履くと足は楽になったが心はもっと重くなってしまった。すぐに参考にしていた涙がまっすぐ、と流れ落ちた。
「よろしくお願いします。本当にありがとう、ジョングクさん」
「·····。」
「本当は大変でしたか?
人もなく知ってくれる人もなく。
ソクジンは言うのが難しいです。
ただ一人でしっかり我慢してきました。」
「·····。」
ただ、ただ私は他に何も必要ないし・・・大丈夫かという言葉一言聞きたいのがだったのに。本当のそれだ。両手で顔を覆ってふらりとした。ジョングク氏はそんな私に近づき、慎重に背中を吐きながら生きて私を抱きしめてくれた。

「泣きたい場合は泣いてください。キム・ヨジュさん
泣くと誰も何もしません。」
「·····。」
「・・・今は私のトップマネージャーじゃなくて
知っているお兄さんだと思ってください」
「·····。」
「私はあなたの心をすべて理解しています。
わかりました。」
ジョングクさんが話を終えたやいなや、私はさらに泣いた。止めたくても涙が止まらなかった。そうすれば、本当のジョングク氏がその時の記憶を蘇らせてくれた。私が大変だったとき、唯一の隣に残っていたその兄。
'今何が心情なのか知っています。だから
泣いて、ヨジュこういう時は泣いてもいい。」
ジョングクさんが必ずその兄のようだった。今は顔も名前も記憶がぼやけているが、行動がとても似ていた。その兄がまだ私のそばにいたら、私はジョングクさんではなく、兄に頼っていたのだろうか。

「少しは泣いても大丈夫です。
できて守ってくれる人がいるじゃないか」
そうしたら、おそらくその兄もジョングクさんと同じような話をしただろう。
サブ波を手に入れる〜
