
10

「入ってください」
「ジョングクさんも気をつけてください」
そう家に着いた。ジョングク氏は入るという言葉を終えて後ろを回った。ありがとうございましたが、私ができることは何もありませんでした。なんでもしてあげたい気持ちで歩き回るジョングクさんの手を無作にとってしまった。
「え…。あ、それが・・・」
「·····。」
「..ありがとう!私はやります。
できるものがなくて・・・。」

「·····。」
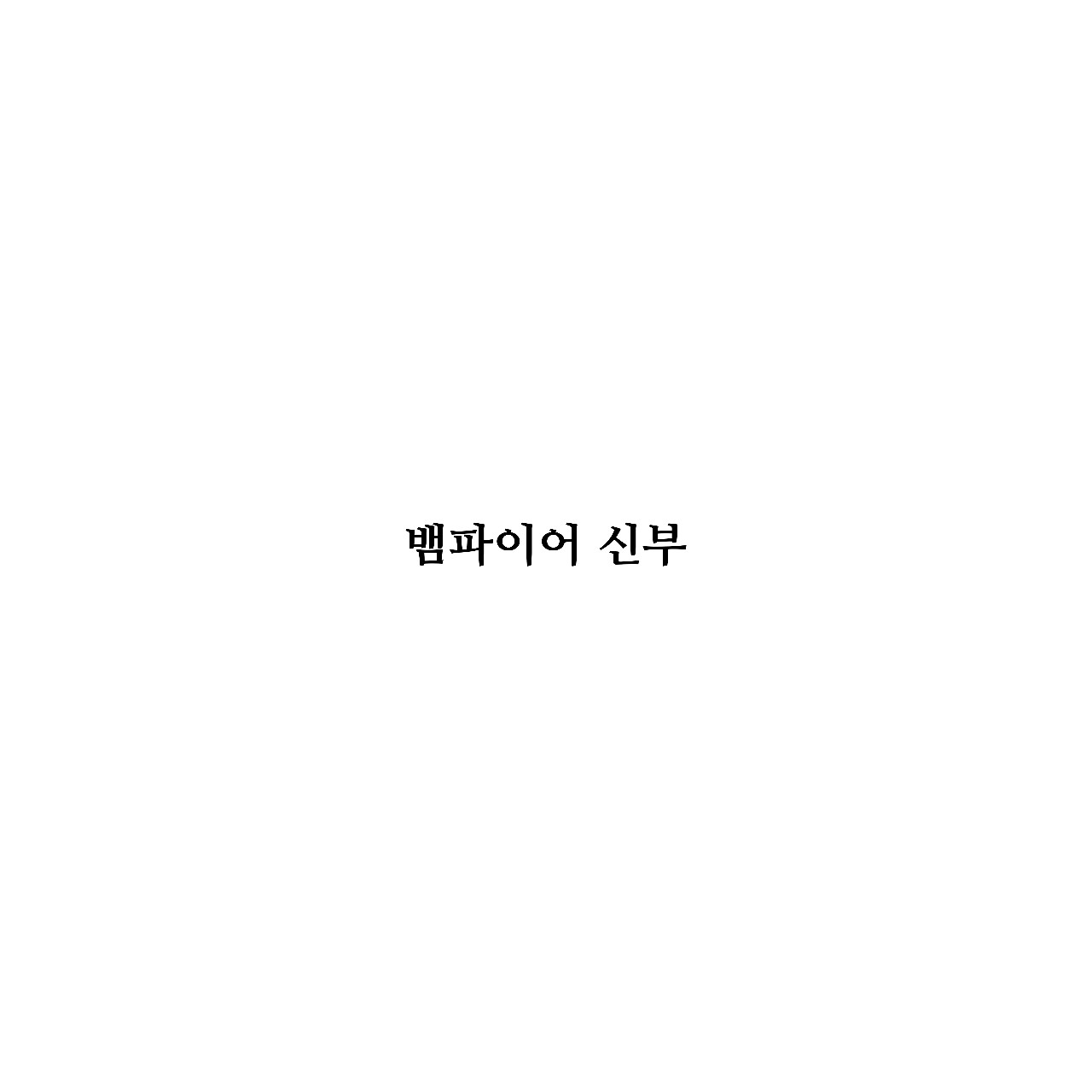
「そこに」。

「·····。」
「これ落としました」
7年前、19歳。真っ最中勉強しか知らない年齢でその子が現れた。 「キム・ヨジュ」。二重まぶたがないにもかかわらず、目の細かい、小鼻、薄いがきれいな唇。小さな顔に凹凸目の鼻がよく入っているきれいな子供だった。
ヨジュはいつも人気が多かった。それが理性か同性であろうと。その間に私がつかむ席はなかった。ただ遠くから見守っただけだった。近づくには女主人がとても輝いていて、私は四角い角のメガネに、友達もなく、気をつけ合うことのない子だったから。
「女、女主よ・・・」
「·····。」

「お前…泣いて・・・?」
ある日は夜遅くに真っ暗な読書室に一人で泣いているヨジュを発見した。私を見てびっくりして慌てて涙を拭いて明るく笑っていないとバッグを手に入れていく女主に心配になって勇気を私の同じ方向なら一緒に行こうと尋ねた。ヨジュはしばらく悩んだら、すぐに分かると頭をうなずいた。
「私があえてあなたにしても
なる言葉なのかは分からないけど・・・。」
「·····。」
「大変だと泣いてもいいよ
誰も何と言わないから」
「・・・・・・ありがとうございます。」
ヨジュはとても大変で疲れて見えた。互いの長さが交互に別れたときに、ヨジュが先に番号を尋ねた。心臓が狂ったようにすごい電話番号をよく入力したのかもよく分からない。女主の目つきが悲しいだけだった。
しかし、以後連絡は来て行かなかった。ただ番号をやりとりした日によく入ったかという安否メッセージ一つ抜いては。それでも何になってもよかった。存在感はなくても女主の世の中に私が入ってきたようで。女主が知らないことを望んだ。こちらも足りない私が、私を狂わせるのが好きだということを。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――…

「·····。」
- 今来てくれたら、ダメですよ・・・?
トゥク。
「・・・ヨジュよ。ヨジュ?」
なんと一ヶ月ぶりの連絡だった。ところで、ヨジュがまた泣いていると誰が知っただろう。その寒い天気にアウターも手に入れず、外に出て公園に向かって走った。到着して周りを見回すと、ヨジュがパチパチとベンチに座り、少し震えて泣いていた。私がそばに近づいて何が起こるのか尋ねたので、やがて安心して倒れるように私の肩に上体を期待した。
「先輩・・・。あまりにも大変です・・・」

「·····。」
「周りに人がとても多いのに、
中身を知っている人は誰もいません。」
「·····。」
ただすべてをあきらめたいです。人々の秘訣を合わせてくれるのもやめたくて、外面だけ見て近づいてくる人たちの縁も全部切ってしまいたいのに・・・、それはダメです。罪悪感があって女主に直面することができなかった。私も女主の外面だけ見て好きだったんだから。そんな私が女主の心をすべて知ってもいいのかと思った。
言葉なしで女主義などを吐いた。心臓が爆発するようにすごい。好きで震えてるのではなく、ごめんなさい。言えないほどごめんなさい。女主は下炎なしで泣いた。私の手を丸く巻いて握り、必ず握っておいてくれなかった。申し訳なくても女主のそばにはいけなかった。手を引き出そうと、女主が私のワラクを抱きしめた。
「・・・お兄さん」

「·····。」
「ジョングク兄弟」
「·····。」
「兄もいなければ私・・・」
死んでいます。女主の一言にすべてが崩れ落ちる気分だった。このようになった以上、私が考える「女主のための行動」ではなく、本当の「女主のための行動」をしなければならないと固く誓った。続いてヨジュよりも強く抱きしめて言った。
「どこに行こうか」
「·····。」

「誰もが全部去っても
私は必ずあなたのそばに残るよ。
「・・・ 吸う」
「心配しないで、ヨジュ」
少し蹴られた袖の中の女性の手首にナイフで描いたようなかなり深くファンの傷があったが知らないふりをした。女主が私にあまり頼ってしまうのが良いだけではなかったから。ただ、女主の感情ごみ箱だけになりたいと思った。気楽に休むことができる、そんな人になるには私がすみませんでした。
「・・・・・・なんですか・・・?」
「転校に行ったと。
出てこない田園地帯に降りた。」
そうして翌日、電話を受けない女主に担当先生に聞いてみると、誰も知らない田舎村に引越しに行ったという話を聞くことができた。足に力がほぐされて、ふわふわと座り込んでしまった。きっと昨日までだけでも俺の前にいたじゃないか。やっと7時間前までも俺と連絡してたじゃないか・・・。すぐに学校を出て女主の家に向かったが、「賃貸問い合わせ」が書かれている紙以外には何も発見できなかった。

「ヨジュヤ・・・ヨジュヤ・・・ヨジュヤ・・・・・・」
「ミンヨン、ごめんなさい、私たち」
「·····。」
「別れよう」
ヨジュとの記憶は学生時代の一つの思い出として残しておこうとしたが、不思議なほどそれ以来誰かを愛することができなくなった。どんなにきれいな女性を見ても、どんなに心のこもった女性を見ても何の感情も聞こえなかった。だから好きではないのに付き合う相手が傷つくことが大半だった。
「ああ、本当に最悪だ」
「·····。」
「必ず兄のような人に会って
同じようにしてください。」
私も知っています、私は最悪です。
席を浮かべる相手に何も言わず空の酒に焼酎に沿って飲む城にお茶を入れて首の中に渡した。書いた。ヨジュのように。甘い。ヨジュのように。書くが甘くて憎めない、そんな。

「・・・めちゃくちゃだね、ファック」
初恋というのはあまり利己的なのではないか。
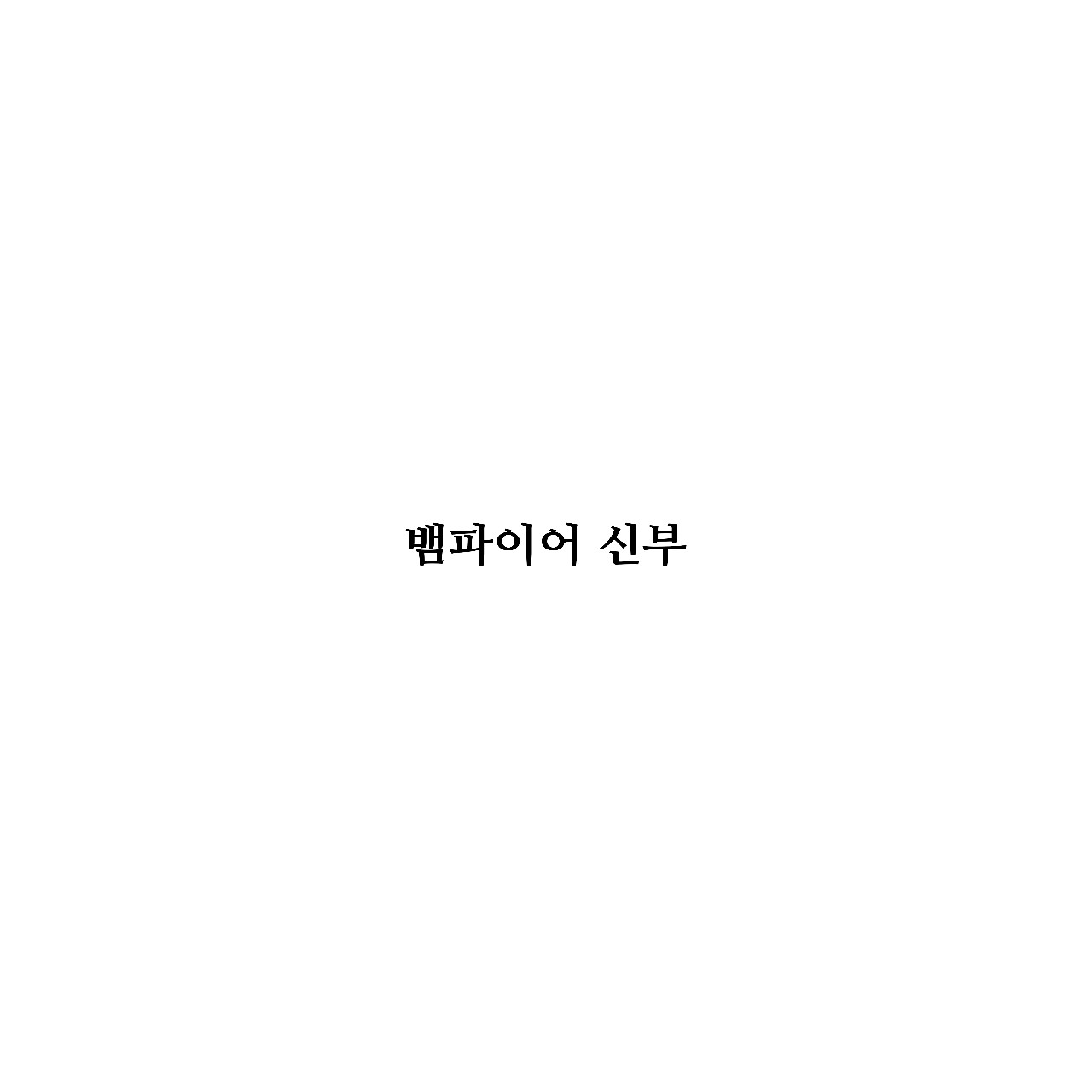

'泣きたい場合は泣きなさい。キム・ヨジュさん
泣くと誰も何もしません。
「大変だったら泣いてもいいよ。あなたが泣く
誰も何も言わないから」
きっとその二人は似ていた。ジョングクさんが私を兄のように考えて期待していた時、明らかに7年前、その時の感情が咲き誇った。その時、その兄は名前も顔も何も覚えていない。あまりにも古い記憶だからそういうことにしては、その兄の行動一つ一つが鮮やかに覚え難いんだな。
「メガネ・・・、メガネをかけて
あったようだが」
兄の顔がとんでもない記憶が出た瞬間、ソクジンが家に戻っていつ入ってきたのかとしばらく訪れたと叫んだ。すぐに洗って休むという言葉を最後にソクジンが出て洗う準備をしようと笑顔を脱ぐと、手首にある長い傷が目に入った。
今日従って、非常に気になる傷だった。
うんざり!
