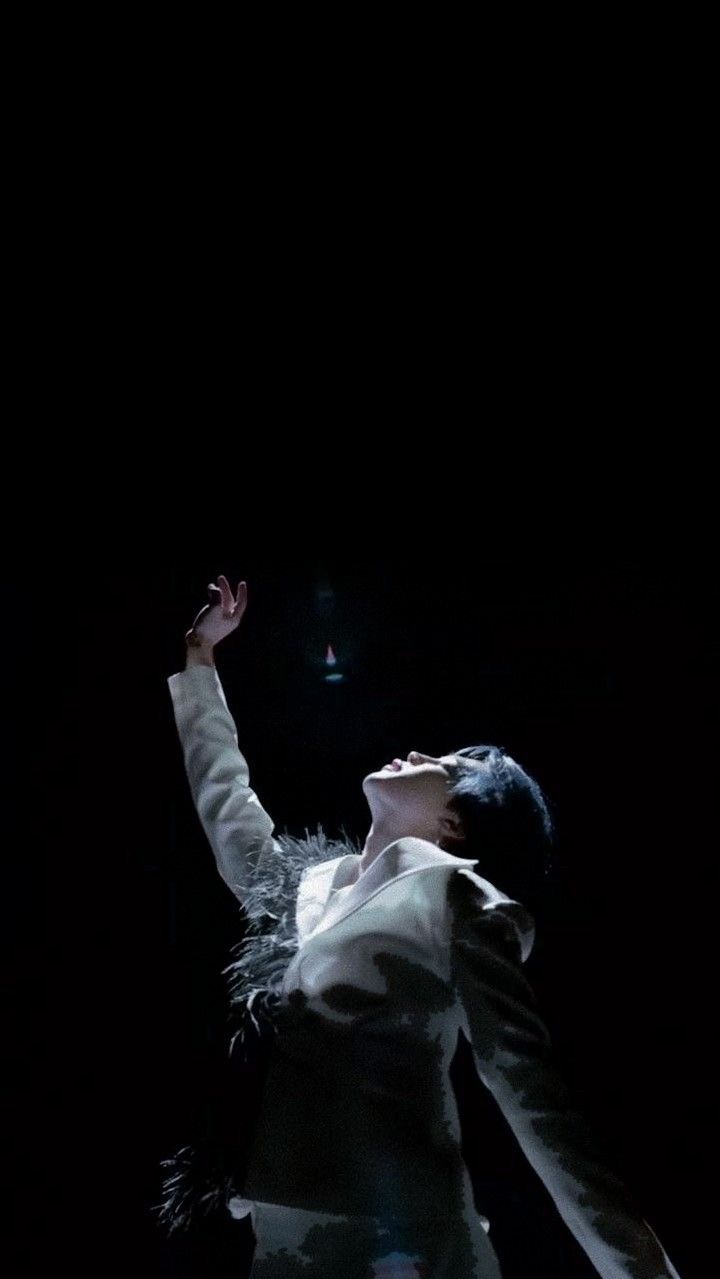
灰色
ㅡ
多くの人に濃い余韻と感動を残す作家で有名な私。しかし、感動的な文章を書く私の人生に感動とは存在しない。毎日繰り返される日常のこととはただ書くことだけ。凍った日常に閉じ込められているのは私も、読者たちも同じだ。
黒色も、灰色も光だが輝かない。では、なぜ光なのか。私の人生は灰色で、灰色は輝かない。ただ私の本だけが輝くだけ、輝く本を書く作家は黒い世界に閉じ込められている。いつ頃、この灰色の中から抜け出すことができるだろうか。いつ頃私にも感動というのが訪ねてくるだろうか。
/
仕事があって書店に行った日。ベストセラーはもちろん、小説部門1位に上がっている私の本を見て私の顔は固まっていた。ベストセラーは幼い頃から成し遂げたい夢だった。だが直接その姿を見ても、私の本に触れても嬉しくなかった。私が感じる感情に肯定的な感情はなかった。一番上から輝く本の一冊のせいで私の人生が黒く染まったので。
私は目の前で本を読んでいる人を見ました。立って本物を覗く一人の男、彼はどこか私に似ていたようだった。外的な部分が似ているのではなく、黒色の世界に住むようだった。焦点なしで本を盗む目、感情のない手振りの両方。私は衝動的にその人の手首を握った。彼は何も言わずに私を見ました。
「…大丈夫ですか?」
衝動的な行動に衝動的に出てきた言葉だった。私がその言葉を取り出す状況なんてできないことを知った。私も灰色の世の中に閉じ込められ、ホウ的距離だけしていたから。私が私を救うことができなければ、私と同じ状況にぶつかった人でも救うことを願う私の心なのだろうか。ただ来ると思うかもしれない。しかし、私は他の人のために私をすでに捨てています。
「…」
彼の口尾は片側に少し上がり、あっという間に消えた。私はわかった、その表情が何を意味するのか。狂うように大変だが大丈夫か尋ねる人に言うことがないときにする表情だった。状態だけ見ても大丈夫かという言葉が出てくるレベルではなかったから。
「…大丈夫なことを聞きましたね、質問を変えますよ」
「なぜ大変だったの?」
「…」
彼は何も答えずに頭を下げた。ふくらんでいるような音で床に落ちる涙が一滴。他の人には来ると思われるかもしれませんが、私はこの男を一気に調べました。一人で灰色の世界に閉じ込められて光を見るために足を振った彼を、私は調べた。初面といっても私は力になってあげたかった。私が私に力になる存在ではないことを知るので、他の人にも力になってあげたい。
「席を移動しますか?」
彼は何も言わずに頭をそっとうなずいた。私は彼の手に聞こえていた私の本を再び差し込んだ後外に向かった。彼は群馬なしで私に従った。私はただ私を信じて従ってくれる彼に感謝したいと思った。
私たちは近くの公園のベンチに座った。ニョンモクになっていく夕焼けを見ていると、いくつかの想念が経ったが、後にしたままその男を見た。余韻が残ったのか、まだふらりとする彼を見て、私は背中をそっと叩いてくれた。彼は驚いたと頭を聞いて、私は少し微笑んだ。
「…私大変だとどうやって知りましたか?」
「その本を読んでいる方はほとんど大変な叙事詩を持った方々だったんですよ、表情もそうだ」
「…そうです、彼の本は感動と慰めを渡します。」
「うーん…私は幼い頃から踊るのがとても好きでダンスを専攻しました。」
「大会に出ない時は練習せずに体調管理をするのが普通ですが、私は強迫のため毎日練習しなければなりません。」
「骨が折れたり歪んだりしても、爪が聞こえても、血が鉄を流れても…ダンスに売り切れました。」
「…私はトラウマがいます、私と一番親しい友人が死ぬ事件が一つありました。」
「何かに集中しなければ、その友人がどんどん思い出して狂ってしまうと思います。だから…踊ったり本を読んだりします」
「その作家様の本は何度読んでも余韻が濃く残って慰めになりますよ、感動はもちろん。」
「みんな違う人生を生きる人たちがその本を読んでみんな同じ感情を感じるということ、それが作家様が偉大だという証拠です。」
「…私が両親も友達もいなくて打ち明ける人が必要でしたが、私の話を聞いてくれてありがとう」
「話でもいいから楽ですね、誰かはわからなくても」
感情が賑わったのか、自分の話を無限に打ち明ける彼。彼の叙事詩を聞くと目が赤くなるのが感じられた。その友人を思い出さないための方法をダンスに選んで毎日苦痛に苦しんでいる。好きな踊りをしながら自分を殺している。彼は自分が雨の黒い世界に自分自身を閉じ込めた。
「もうそっちの話もしてください、そちらも…大変な叙事詩があるようだが」
「…私は、そちらが見る本を書いた作家です」
「すべての人に感動を与え、濃い余韻を残す本を書く私の人生に感動はありません。」
「なぜか灰色の世界に閉じ込められているような気分に苦しくて、息が詰まります」
「ベストセラーと1位に私の本があっても、全く嬉しくないです。」
「その輝く本のために私は灰色の世界に閉じ込められているからです。
「私が他の人に感動を与えるように、私も他の人に感動をして光を受けてほしい」
私が私の仕事を明らかにしたまま、すべての心情を打ち明けたとき、彼はパック驚いたようだった。当然の反応だ。自分が最も尊敬し、みんなに尊敬される作家が自分の否定的な心情を明らかにしたので、ひどく驚いただろう。
「…あなたが、その作家なんですか?」
「想像していた姿とは大きく違うでしょう? 元気で堂々とした人で包まれた作家が憂鬱な姿とは。」
「…はい、そうですね」
「しかし、私はいいです、作家が私の人生をもっと共感してくれると思います」
「私に同質感を感じたまま近づいてくるのかもしれませんが、私は作家と率直な友達になりたいです」
「作家様は私の、私は作家様の日光になってくれたらどうでしょうか?」
そう私たちはお互いに心を打ち明け、慰めを与える率直な友人になった。私たちが経験したすべての叙事詩を打ち明けたまま心情を表わすと心が一層軽くなった気分だった。しかし、私の世界はまだ曇った色を維持していました。
心も軽くなって笑顔をすることも多くなったのですが、なぜ私はまだ灰色の世界に閉じ込められているのだろうか。私はいつ頃から抜け出すことができるだろうか。まだ一幹の光しか入っていない。私をただ光でいっぱいに満たしてくれる人はいつ現れるか、現れるのか。すべてが疑問だらけだ。
私は思ったより安易だった。私の明るい日差しになってくれる人は近くにいた。私が灰色の世界に閉じ込められていた理由は、私の心が完全に開かれていないということでした。私は今まで私に近づいてくるすべてを打ち出しました。私は自分でさえ疑い、心を開かなかった。
だが今や悟った。彼は私の心を開くために苦労し、私はその心を固く閉じていました。毎日私を殺したのはその誰でもない私だった。私を灰色の世界に閉じ込めさせたのも私だった。そんな私を灰色の世界から取り出せるのも、私だ。
私に一幹の光になってくれたジミンと一緒にすれば恐れることはなかった。ジミンはすでにダンスという強迫から抜け出して新しい試みをしていた。もちろんダンスが好きだったので、完全にあきらめることはできなかった。ジミンは私と一緒にする時間が長くなるほど翼を広げた。
私は彼と一緒にいる時間が長くなるにつれて彼に近づきました。初めて感じる感情が彼に感じられ、その感情がどんな感情なのかはすぐに分かった。私はいつか彼に愛を感じていました。
私たちはお互いを愛していました。タフな叙事詩を克服したままお互いに光になってくれ、すでに濃く刻まれた痕跡をさらに濃く染めた。私たちはいつのまにかお互いに深く染めて感動を与えていた。灰色の世界に閉じ込められていた私たちは、お互いに美しくも明るく輝く日光になってくれた。
