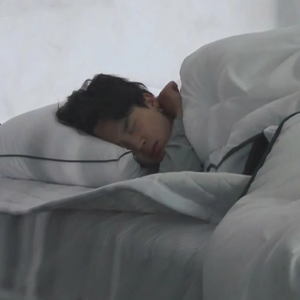うまくいく
「や、や。来た」
「すぐに撮らなければならない」

「…」
空っぽの目の男が空所の前を守って座ったのか一日が過ぎた。タバコを吸うために空所を守ることができなかったしばらく鳥に記者たちがうっとり込んだ。目の前に飛び出すシャッターライトに抵抗する力を失ったように、彼は静かに目を閉じた。すぐに聞こえてくる記者たちの叫びに再び目を覚ました。
「故人の極端な選択、
いつものことを推測していましたか?」
「今後の活動計画はどうなりますか-」
「打殺で疑われる情況はありませんか」
「一言だけください」
彼は口を開いた。シャッター音さえ減った。みんなが息を殺した中、すべての視線が彼に向かった。
2ヶ月前、
窓の外に白い綿が散らばっていたある日だった。早いペースで降りこんだその目がどんどん増えてきた夜がひどくなった。通昌の外に見える目を見下ろすことなく見た。目が本当に涼しいと実りない考えをして。
それからあなたが来たのです。とても嬉しい超人種を鳴らして。インターホンでしばらく見ました。鼻先と顎先端が赤くなったまま薄い笑いを帯びている君を。頭に結ばれた雪片を振っても見て、寒すぎる残りの手にホホ着を吹いても見る君を。まさに扉を開けてくれない私が気になったのか、あなたはもう一度人種を押した。さて、私は玄関門に向かって長く続いた廊下の上を走った。

「見たかった」
彼はドアが開いたとすぐに私の腰を包んだ。パジャマの上に感じられる冷たい手の寒気にしばらく掻いた。彼は私の肩の上に頭を落とした。やっぱり冷たい。
彼は私を抱えたまま玄関の門を照らして入ってきた。アヒルのように背中と背中を歩いた。一、二回ではない人のように、玄関の前に置かれた室内スリッパに足を押し込んだ。ハンギと混ざった彼の向きが鼻先に押し寄せてきた。私をソファに座り、私は台所に行き、水に従った。
「私たちはいくらですか?」
「一ヶ月くらいになった」
「よく行ってきた?」
いいえ
彼は言った。彼は最近映画撮影スケジュールのために休むことなく仕事をしてきた。去る一ヶ月間捕まった海外撮影で精神なく忙しい日を過ごした彼と久しぶりに会う日だった。帰国するとすぐに私に走ってきた彼が奇妙にならないことができなかった。
私は病気です
馬が落ちるやいなや、私は彼に近づき、状態を調べた。幸い、額には熱がない。体温計で見ても異常症状はない。
「今は大丈夫」
「本当に?」
「体肉だったみたい」
安堵のため息が節に出た。幼い頃から冬の風邪だけは毎回避けることができなかった君だった。体でも丈夫な三十になって妄想だし、お前の幼年は病院で過ごしても過言ではないほどお前はよく病気だった。両家の母親の親しみで、私はいつもそんなあなたの隣を守っていました。私の手持ちの注射針を手の背中に挙げて、スプーンにすらしにくい君にご飯を食べさせてくれるのは私の分け前だった。
そんなたびにあなたは笑い声で出て結婚をすると言った。当時は10歳だった。あなたのご飯の上におかずを上げるたびに、雷を怖がっているあなたの隣で子守唄を呼ぶたびに、病院の米を嫌うあなたのためにイチゴのお菓子を手に握るたびに。あなたは同い年である私に、結婚のようなものを何度もやりました。私が大きければ、結婚は必ずあなたとしなければなりません。
「どう思う?」
「ただ…星の考えではない」

「強い顔を見てみよう」
いつの間にか水のカップを空にした彼は私の隣に来た。ひざまずいて横になって私を見上げた。じっと見たら、まさにそのまま大きかった。片方は二重カップルがあるが片方はない目。時には遊び心が混じって見えながらも普段は限りなく深い瞳。あなたの顔を盗む私の目を意識した彼が耳目口比を存分に掴んで面白い表情を見せた。無実の笑い声が飛び出した。
「完全に醜い君」
「どう思うかとあなた」
「…」
私はどう言うことができますか。君との恋愛をやってきた大衆が分かったので、ちゃんと息を休んだことがないと。毎日のように夜になると未知の誰かから電話が数十通ずつかかってくると。毎朝、玄関口を開けると、悪意を持って目が破れた私の写真が床を転がっていると。寝ると誰かから剣に刺されて死ぬ直前の夢が繰り返されると。睡眠薬を食べてもその効果が聞こえないと。
「抱きしめて」
「…」
「寒い」
「…」
尋ねても答えないだろうということに気づいた君が私を見た。横になっていた君が 起きて私の隣に座った。待っていたように、あなたは私の胸に入ろうと思うまで体をくしゃくしゃいますが、その姿が笑って私も知らずに笑った。君がいなかったその間、私が作った悪夢が全部飛んでいくようだった。
。
私たちが10歳になったその年は、あなたが有毒な風邪をひどくしました。体の炎症の数値が高く、一ヶ月近く入院生活をしていた君に、雪上家として悪い知らせが伝えられた。お母さんが交通事故に戻ったというニュース。状態が悪いので、医師はあなたが病院にいることを勧めました。そんな理由でお前はママの最後を守れなかった。
あなたが歩く前に、あなたの両親は離婚しました。お母様一人でお前の病院費を負担して生きておられた。帰って以来、あなたは言葉がなくなった。もともとなかったが、さらに口を開こうとしなかった。私の家族も裕福なたるみにはならず、助けを続けることができる状況でもなかった。私たちはただ希望という同じじゃない言葉で、貧しい命を延長していたのか。
。
。
あなたが芸能界の足を踏み入れたのは恣意ではなかった。お金がなく、お金を用意しなければならなかった。ついにあなたには外れたルックスがあった。それがお金になった。あなたは15になった年にキム・テヒョンという名前で映画界にデビューした。予想通り大衆の反応は熱かった。そう15年が流れたのだ。
お母さんの言葉によると、私は幼い頃、だから今は記憶もない四十歳の頃に衣類広告を撮影していたモデルだったという。それで稼いだ収益がかなりなので、ママは続けたいと思ったというが、保守的なお父さんのために以後は学業に邁進していたようだ。
別の道を歩くようになったあなたと私が遠ざかると思った。もう二度と見ることができないと思った。しかし、私の心配とは異なり、彼は私との出会いを乱す方法がありませんでした。毎日のハギット路地で私を待って、朝夕に安否を尋ねる連絡をしてきた。時にはビデオ通話まで。幼い頃、口癖のように言っていた請婚を本当にでもする勢いだった。あなたと私は本当に…したら?腐り悪くないと思ったのも事実だ。

「お元気ですか?」
私の人生が丸ごと揺れ始めたのはその時からだった。映画とドラマ、広告界まで摂れた俳優キム・テヒョンが一般人と長い間交際してきた事実が満天下に現れた時。彼は記事が現れるとすぐに電話をしてきました。どうせ神像が明らかになったわけでもなく、まあ、あまり問題ないじゃない?心配するあなたを考えても平気なふりをした。
それからあなたは言わなかった。記者が記事を破ったというのは私の顔を知っているのだと。国は存在をいつでも大衆が知ることができるのだと。 私は大変になるだろう。
3日前、

「連絡ができないって?」
テヒョンが尋ねた。マネージャーの相次いで通話の試みにも導く黙黙の答え。電話を受けていない。きっと今日はスケジュールがなくて家だけにいるはずに連絡ができない。テヒョンはなぜか分からなく不安になった。この状況で今後30分後に捕まった生放送は後戦だった。ティーを下ろそうとするが、みんな現れる顔だった。
「できない」
「何をどうするの?」
「行かなければならない」
「冗談だよね…?」
テヒョンがメイクを受けずに立ち上がった。突然、マネージャーの顎に沿って汗が流れ始めた。本当に行ってもならこれは大型事故だった。所属事務所レベルで収拾するのも大変な事故。席を立てるという彼の一言に待合室の雰囲気が沈んだ。マネージャーの万流にもかかわらずギアコ行くとコートまで手に入れた真だったのだろうか。マネージャーの基本着メロが聞こえた。
ました。
「こんにちはドハヤ」
マネージャーが驚き恐ろしくテヒョンがまさに拾った。全神経が携帯電話越しの音に向かって急いでいた。誰もが息を殺した。
「強くて、答えをやってください」
「…うん、テヒョン」
少しロックされたようなドーハの声に呼吸する方法を忘れていたテヒョンが近くに呼吸を吐いた。さて、スタッフ全員が胸を掃きながら安堵する雰囲気になった。

「なぜこんなに電話できないのか」
「…睡眠薬を少し」
「うん」
「たくさん食べたみたい」
「…」
「薬が入らないから」
「…」
「ランダムに打ち込んだら」
「…」
「私は知らなかった…」
テヒョンは知っていた。ドーハが不眠症に数年目苦しんでいるという事実を。でもやってもらえることがないので毎回横から見守ってみるだけ。ドーハが悪夢を見て途中で目が覚めたら、言わずに背中をあきらめて抱きしめてくれるのが彼のやり方だった。
極性ファンのためにドーハが苦しむこともわかった。所属事務所側に数回話し、また所属事務所それなりに俳優とその側近保護に総力を傾けていた。それにもかかわらず、防げない被害がしばしばあった。テヒョンはドーハが経験している被害について全部知らなかったし、ドーハは知らせようともしなかった。
「それでは危険だと言ったでしょ。」
「…うんわかる」
「食べたいのは」
「みかんを食べたい」
テヒョンはなぜか胸が食われるのを感じて他の話題に回すことに急級した。日常的な会話をすれば少しは大丈夫になりそうだった。そのように後で約束し、電話は壊れた。
テヒョンは知らなかった。その通話を最後に再びドーハの声を聞くことができないということ。

「どうして今日も大丈夫だ」
。
。
。

「誰が花で、誰が人ですか?難しい」
。
。
。

「私が今の婚姻をしたら受け取る?」
。
。
。
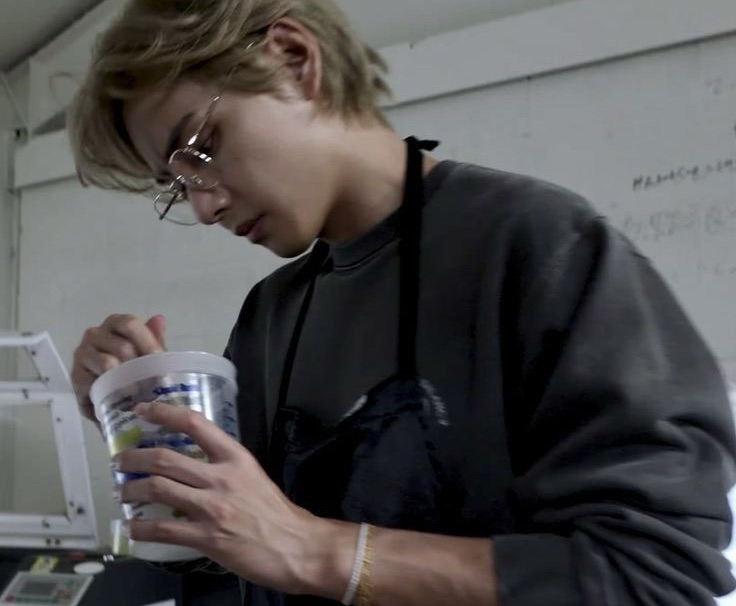
「食べたいものがあれば言うだけ」
。
。
。

「私が間違っていたので、一度だけ見てください」
。
。
。
自分をめぐる記者たちの雄大な音は、声に騙された。テヒョンは慎重だった。記者たちがドーハの名前を汚してはいけなかった。自分が言う一つ一つが彼らには餌食になるから慎重にしなければならなかった。短時間に重ねられる悩みにもかかわらず、テヒョンは結論を下すことができなかった。答えは決まっていた。
私が本当に言ったら、ちょっと変わったのでしょうか。
そうだったら住んでいたでしょうか。
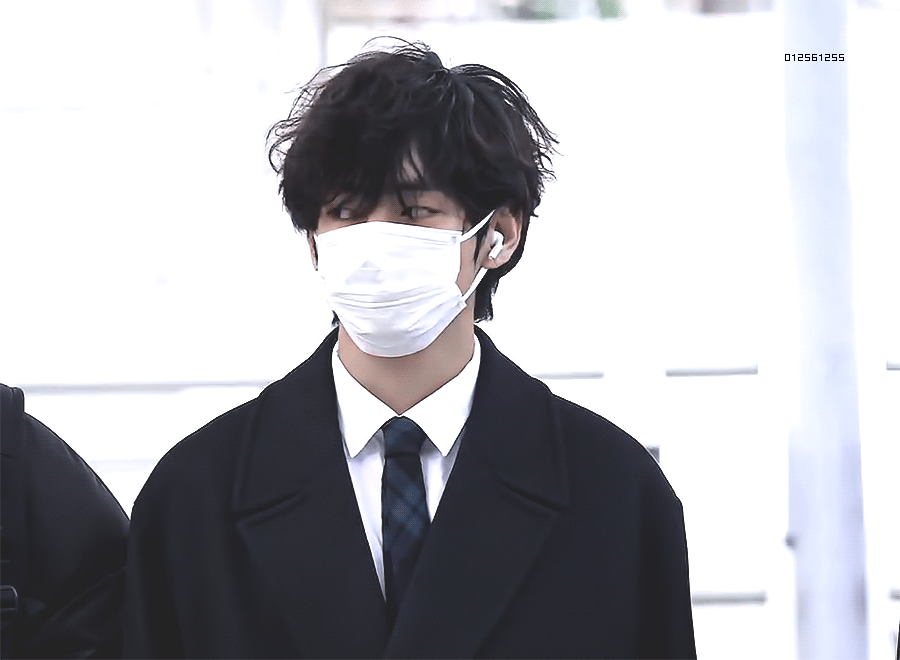
「引退します。」
ドーハのそばに私がいなければなりません。健康です。
その言葉を最後にテヒョンは席を避け、待っていた警護員たちが記者たちを外に追い出した。騒々しい葬儀場の中に静けさが訪れた。
。