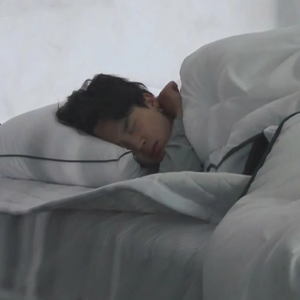金目書、灰皿
。
「キム・テスをなぜ殺したのですか」
「…」
地下はただ一瞬も男の目を避けなかった。むしろ突き抜けて見つめた。

「そうしなければなりませんでした」
これが答えになるか。瞳を一度ドゥルリョク転がったテヒョンが再び地下の視線に合わせた。地下では何の表情変化も現れなかった。答えはこんなヒントもダメですね。
地という事実が気になった。テスの死を哀悼したり、まあそのようなじゃない理由から始まった質問は決してなかった。ただ本当に理由が気になった。私にも何とかあった人があなたにも何のような存在だったかと思って。単にその人の死に与えられた当衛星の種類が気になった。
「愛してた?」
「はい」
愛していました。きっといつかそうしたことがあったでしょう。地下が付け加えると、テヒョンが淡々と地下の言葉に耳を傾けた。妙に喉が舞うような音がするのも同じだった。
「ご存知でしょう。」
「…」
「キム・テスと私の間にそのような関係ではないということ。」
「私がどんな水路、」
「みんな見たけど」
試みる時もなく尾行つけて私監視すること。近くに呼吸を選んだ地下がおまけに吐き出した。微妙な嘲笑が混ざった話声だった。それなりに、私は秘密によく終わったと思ったその蛮行がすべて明らかになったわけだ。テヒョンは予想外の発言に私も知らないように口尾を上げた。
。
6年前の冬、だからテスと地下二人が出会う前。地下は19で、テヒョンは23日です。
テヒョンは地下に最初に会った。
。
「おばさん、水餅の残りを私に売ってください!」
「おや~君をたくさん泊めなさい」
商売の締め切りになっていく遅い夜だった。真夜中を鼻の前に置き、学校で面接の準備をして出てきた高校生が市場分食屋の前に座った。バックパックは何気なく床に投げておき、ロングパディングジッパーをあごの先まで引き上げたままホホ吹いて食べる水餅だった。学生は10個も食べることができるという良い考えをした真だった。
「…」
ウェンブラックスーツを着た男が生徒の隣に席を餅するので握って立った。静かな田舎の床では、非常に珍しい姿でした。妙に映った香りと森の内音が混ざり、私は男から学生は原初的な拒否感を感じたと言った。
「外傷。なりますか」
「はい?」
分食家社長になった。そもそも外傷のようなものが存在するはずはなかった。小さな町の小さな市場に。剣のような経済構造に戻るこの小さい社会へ。隣で聞いた学生も、不思議にしたかったのか一言かかった。
「…ちょうど私のお金を使ってください」
「…」
「何を食べますか」
私の常連の分食屋さん、それだけ長く見て、ジェゲンもなく良い大人のおばさんが困っている様子を見たくなかった。見た目は遠くて中はどこに足りないだろう…男を惜しみなく思った生徒が、大虎や腕のような子犬のようなコイン財布を取り出した。男は一人でしか聞こえないように笑いを吐いた。
「一番おいしいものでお願いします。」
「冷たくよく受け入れますね」
男が風に落ちる声を出してしばらく笑った。普通は中にしかしないような声を面前にし、海台は制服姿の学生を見て堂々と考えたようだ。続いて学生は男に私の分け前だった水餅を渡した。紙コップひとつにかま汁を入れて一緒にくれるセンスも発揮して。
ただ、この男がどこか変だった。水餅自体を初めて見る人だけで餅に刺さった木の箸だけに触れて座ったのではないか。生徒がそれを気づく前に男が生徒が食べる姿を見て、大体気づいたのが幸いだった。
「電話番号ちょっと」
「はい?あの高校生ですね」
「…わかります。」
「…」
「お金を送ろう」
「…あ。」
ハハ。分食家社長がやめられ、笑いを破った。学生は素敵なこの状況を無視しようと高価なものでもないと断るのに忙しかった。されて、ちょうど良いことをやっている。その言葉を聞いた男がしっかりと微笑んだ。
あっという間に餅を食べた彼がプラスチックの椅子で起きた。魚墨スープには手も触れないままだった。木の箸一回、紙コップ一回フックは学生が男を見上げた。
「優しく買ってください」
「はい?」
「私が施した恵みを忘れないで」
「…」
「正しく買ってください。」
男はこの生徒をまた見ることができたら、と思っていた。

「そうか。今日からでも」
それが4年間の一方的な追跡につながったが、だ。
。
再び、現在。
「いつからですか?」
「かなりできました」
「キム・テスと一緒に暮らす時からずっと?」
「…」
地下がテヒョンの両目を交互に見つめた。当최何を言おうとしているのか分からない人だった。ただそんな表情だった。言葉でもちょっとしてほしいな。なぜこの男は答えがない。
「もっと昔から?」
「…」
「私は知らないの?」
「…」
「それでも見てただけ?」
最後にテヒョンの瞳が目立つように揺れる瞬間だった。ずっと自分に向かって注ぎ込んだその唇だけを追っていたその目が、寂しさにひろがる別の目に直面した瞬間だった。どんな理由であっても、間に私を見ただけだったんです。毎日の死の直前で厄介な私を。

「だから殺したじゃないか」
いかなる言い訳もせず、キム・テスの死を語るテヒョンの一言に、今回は地下の目が揺れた。その男が主張する因果関係がまったく信じられないから。ただの言葉だろうと思っても少し前とは違う態度があまりにも異質的だ。例えば動揺する瞳、微妙に震える唇、不規則になった息のようなもの。何よりもため息のように、その間に積もったものを解放させるような言葉が脳裏に刺さって忘れられなかった。
。
翌日、
朝から訪問をノックしてくる音に浅い睡眠で割った地下がロックされた声で答えた。はい。
「朝の時間です。」
「…はい?」
「出て廊下の最後まで歩いて、」
「いいえ、ちょっと待ってください」
「はい?」
「あのもの…王室体験…」
言葉を選んでお茶したかった地下が言葉を無視した。朝はもともと食べません。これからは手に入れないでください。それをじっと聞いたジェヒョンは予想した反応というように気を付けずに次の言葉を伝えた。はい、私も大体は期待していました。でも社長の指示だから私もなんの仕方がありません。
瞬間社長という呼称が見知らぬ地下がテヒョンを思い出すのに少し時間がかかった。次の言葉を中に選ぶ最後に吐いた質問は
「上司は。どこにいるの?」
「出勤しました。」
「いつ戻ってきます。」
「今日の仕事は少し遅れます。」
「じゃあ外出ちょっと行ってもいいですか?」
「はい。ちょうど私が同行しなければなりません。」
「はい?」
「社長の指示です。」
本格的な尾行の始まりだった。