W. ダービー

「上がって育ちますか?床が不便でしょ」
「成長」
「私はそんなに嫌いですか?」
「…」
目をつぶした。犬が吠える時は無視が答え。元彼氏と同寝することになったか、すでにドットが過ぎた。イ・ジェヒョンが現在王子の体で狂って飛ぶほど申し訳なくなった。ジョンナ守ってくれてすみません。
明日はZ国に行かなければならない。体を後退して考えた。
考えてみると、ここに来てから王女の部屋を見たことがなかった。
最初は私の部屋でもなく、他人の部屋を後退するという考えに触れることも考えなかったが、こういうわたしがストレスを受けて倒れてしまったので仕方ない本物だ。
「ジェヒョンああ」
「うん?」
「私たちの現実に戻ったら、もう会わないでください」
「なぜ?」
「…」
.. 言葉は私が病身だ。本当の睡眠も寝なければなりません。
。
。
。
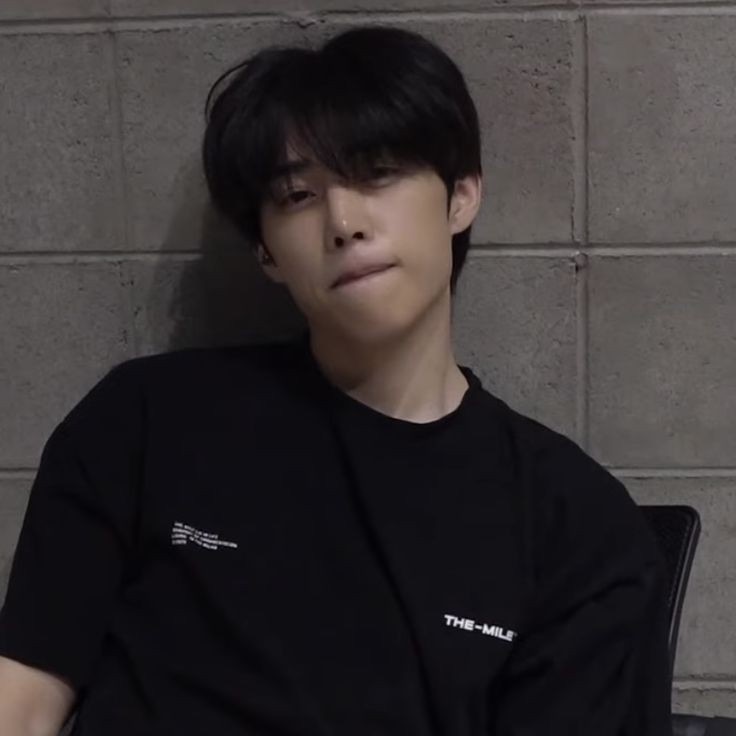
「何なぜ来たの?」
「ああ、私の部屋に何か……置いてきたのが思い出して」
「ああ、あなたはそれでも時計を置いていったので、どうしたのか」
「時計?」
「命のように持ち歩いたら、それを置いていくのか」
私は感じています。時計?プリンセスが命のように持ち歩いたと?
これだ。突然家に帰ることができるという考えに心臓が素早く走った。もうこのおっぱいのようなドレスもグッバだ!
一方では残念な気持ちも聞いた。現在王子と挨拶もできなかった。
ボモと..主演と。そしてまだ名前がわからない最初、第二の兄弟と
午前中にずっと汚れた鳥まで…。
久しぶりに部屋に入ると 振り返っても痛い大きさにベッドの上の宝石箱が載っていた。 うんざりしているのは不思議だったが、暑い拾い上げて開いてみると、ぴったり見ても 古く見える時計が入っていた。
慎重に手首についた。
今目を閉じて浮かんだ..私は..
「…」
なんだ始発…そのままじゃないか。
もともと映画のようなものを見ればこの台木からまた戻ったのに。
そんなもともと人生がこんなに堕落したら楽しくない。ところで、今まで淫らだった人生一回でも面白くてはいけないのか?
「キム・ヨジュ」
今は歓迎まで聞こえた。おなじみの声。イ・ジェヒョンだった。
周りを二度回してもきっとこの部屋の中には私しかいないのに…
これは上司病ですか
「キム・ヨジュが気をつけて」
..え?
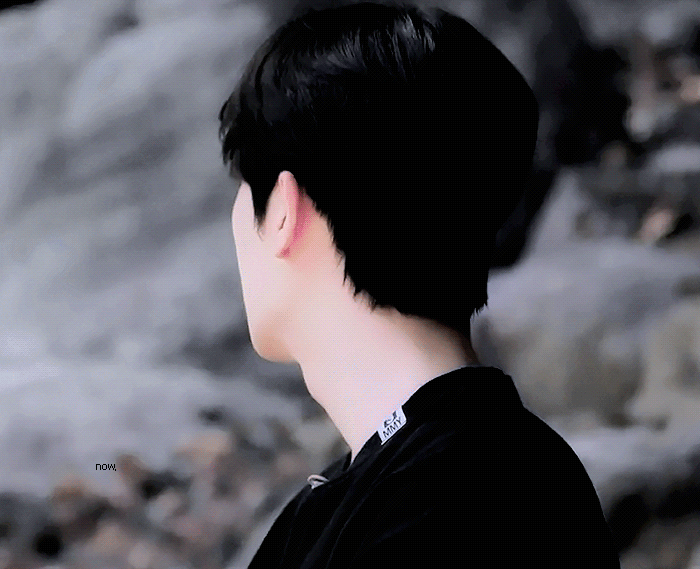
「あなたは大丈夫ですか?わかりますか?」
「..エン?」
「あなたはこれをいくつか見せてください。」
「..一本」
「私の名前を覚えていますか?」
「イ・ジェヒョン…」
「は、幸いだ」
先ほど立っていた私が冷たいベッドに横たわっていた。
久しぶりに見る私の自炊部屋の天井と私を振って目覚めるイ・ジェヒョン。
いいえ、イ・ジェヒョンではありません。
「待って。水を流してあげる」
「…現在王子なの?」
「それまで調べてみようか?
「あなたはなぜここにいるの?私に戻ったの?どうしたの?」
「一つずつ尋ねて」
この巨大な自炊部屋に現在王子は慣れているように冷蔵庫を後ろに生水陵取り出した。見てみると装いも楽に見えた。一度渡す水を蜜っぽく飲みながらも思う整理ができなかった。
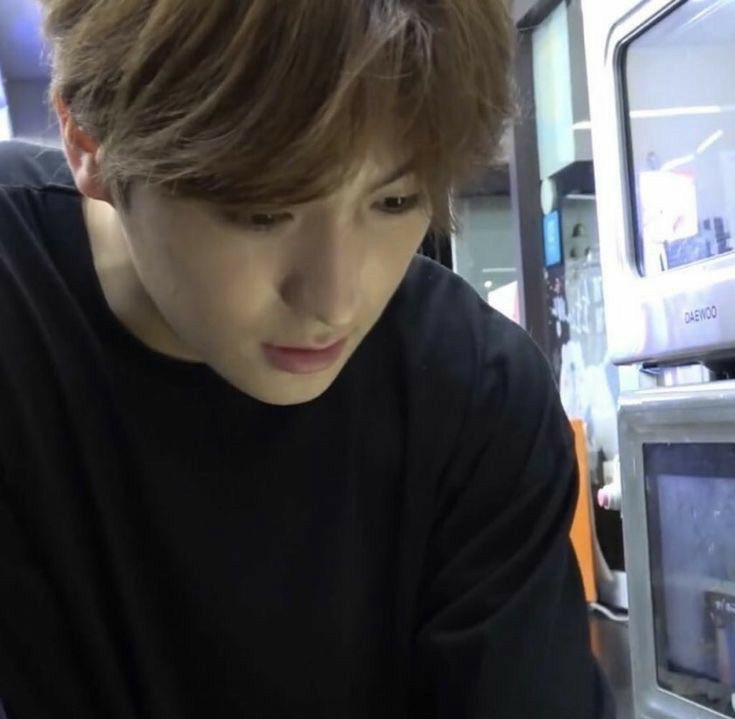
「姫は元に戻ったんだ」
「…あなたは?」
「…私はまだ。」
「どうしよう。
再現がピック笑った。笑いが出るかと。でも俺もチャマガラという声が口しか出てこなかった。ただ..久しぶりに見るのだから。少しでも一緒にいればいいから。
「…いや」
私はここにいるのだろうか?
ベッドに座った現在の王子が淡々と尋ねた。それをなぜ私に尋ねなさい。私が行かないと言えば行かないわけでもない。と言うところだ。
実は行かなかったらいいな。もちろん私の風ですが。
「行かないで」
「行かないと」
「…何の答えが聞きたいのに」
「このまま行けばまた会えないだろう」
「…」
頭をすっかり震えて再現が乾いた顔を掃き出した。じっと彼を見てみると、私が一言しなければならなかった。王子がここでこうしている間、元彼氏が国を開版にしておきますが、どのように行かないかという声を並べてみましょう。本当にイ・ジェヒョンはファック..
「…キム・ヨジュ」
「…」
「泣く?」
「…目が暖かくて」
視界がぼやけた。目がずらりとした犬の声を並べて慌てて席で起きた。トイレでも行ってチュスルして来なければならない。フダダック逃げようと両腕が捕まってしまった。目が合った。目にたくさんの力を与えていたのが無色に涙が流れた。
「行ってはいけないと一言だけ。難しいことじゃないでしょ。」
「…」
「お前…わかるじゃないか。もう好きだ」
どうやって知らない私をこんなに優しい目で見てくれるのに。
「……違う?
「これが…どうやって勘違いなのに」
「同じように見えたから。混乱させることができる。」
「今、吐きは言葉に責任がある?」
「…」
いいえ。私は百人のイ・ジェヒョンがいても、あなただけを見つめる自信があった。
結局この地境になった。気にしてはいけない人を抱いた風に
こんな恥ずかしい別れに胸がとても痛く裂けそうだった。

「私は間違っていません。私の感情は私が最もよく知っています。」
「…」
「..だから言ってください。どうぞ」
「イ・ジェヒョン」
..行かないでください。
やっと吐きは短い言葉にも唇がパルル震えた。今回は両頬が捕まった。慎重だが緊急に私の唇を噛む行動もあまりにも現在の王子だった。
頭を包んだ大きめの手が下がり、私を引っ張った。胸が当たった。隙間なくイ・ジェヒョン品に抱かれてしまった。汚れてワクワクした。
口の中を軽く混ぜる舌。狭くて冷たい部屋の中。すべてが夢のように感じられた。ここが現実なのに。
「..これでもいい?」
「目を閉じて」
「..いや!これでもいいかと。 もう一度帰れないと、っ、ちょっと待って」
突然、現実的な考えに肩をすくいても夢を見ない。
置いてきた主演と今すぐ姫と婚姻する元彼氏イ・ジェヒョンが心配ではなく心配になった。国を台無しにしたらどうですか?
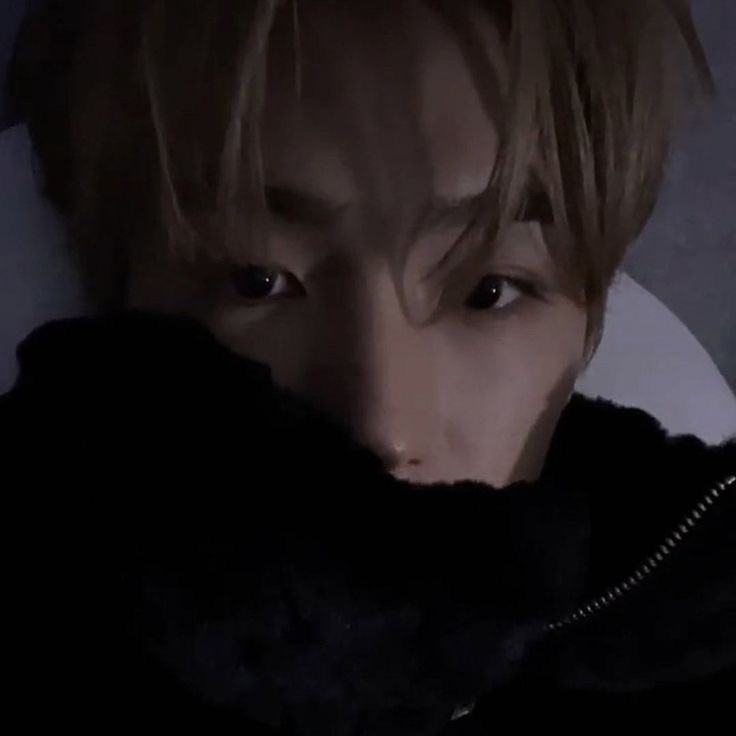
「雰囲気が落ち着かない。キスもすべきではない?」
「ええ、それは一国の王子だったでしょう」
「プリンセスに頼んだ。今ごろ元の彼氏のプリンセスに焼いて食べているんだ」
「…」
「イ・ジュヨン 걔も帰るんだ。伯爵じゃないようだとは大変気づいていた」
「…」
「だからやめて心配してる。全部終わったから」
私が目を覚まして私の唇をぶら下げると、私は本当に体の両方を知りません。唇が近づいてくる。知りながらも避けなかった。代わりに目をスルリュック巻いた。
****************
談話最後の怒りのように!
